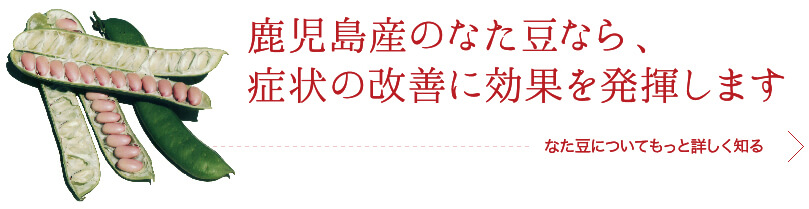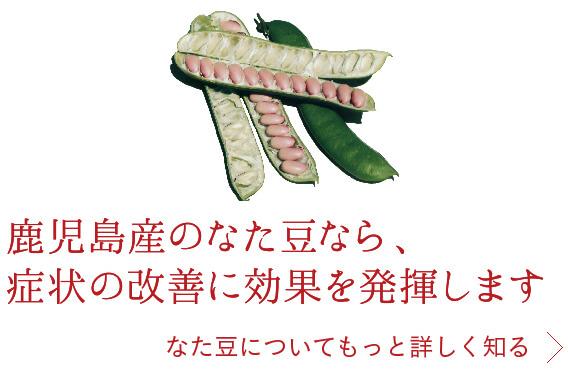腎臓病

腎臓病
腎臓は、体内の老廃物をろ過し、血液や体液などを健康に保つ大変重要な臓器です。
一口に腎臓病といっても、腎臓の病気にはさまざまな種類があります。実は、腎臓病という言葉は腎臓の機能を低下させる病態の総称なのです。慢性腎臓病(CKD)
腎臓病の中で近年患者が増え続けているのが慢性腎臓病(CKD)です。
慢性腎臓病とは、腎機能が健康な人の60%以下に低下し、タンパク尿が出るなど腎臓の異常な状態が長く続く状態で、治療しないでいると、腎機能がどんどん低下してしまい、透析や腎移植が必要になります。
慢性腎臓病は、ほとんど自覚症状がありません。慢性的なだるさ、むくみ、息切れなどの症状が現れたときには、症状がかなり進行しています。早期発見のためには、定期的に尿検査や血液検査を受けることが大切です。慢性腎不全
慢性腎臓病が、数ヶ月から数十年の年月をかけて徐々に進行するのが、慢性腎不全です。
いったん慢性腎不全になってしまうと、現在の医療技術では腎機能の回復は不可能で、徐々に腎臓の機能が弱っていきます。
慢性腎不全を治す薬はありません。しかし、食事療法などを併用して、進行を遅らせることはできます。腎臓病の食事療法は、たんぱく質と塩分を制限して、体の中にできる老廃物の量を抑えていくことが大切になります。
腎臓病(慢性腎臓病)について 先生の話


腎臓病(慢性腎臓病)について 先生の話
はるかなれいクリニック院長
医学博士 井上隆人先生
なた豆と腎臓
なた豆は歯槽膿漏や蓄膿症などの「膿取り効果」で知られていますが、腎機能の改善にも効果を期待されています。
なた豆には、尿素を分解する働きのある酵素「ウレアーゼ」が多く含まれています。ウレアーゼが腎臓でしっかり働いている事は、腎機能が正常な証拠にもなります。したがって、ウレアーゼの豊富ななた豆は、腎機能を改善する可能性があると考えられます。
そもそも膿は白血球などの死骸で体内の老廃物のひとつですが、腎臓はその老廃物をろ過する器官です。したがって、膿取り効果で伝えられるなた豆が、腎臓病にも効果があるというのは納得がいきます。
古い文献にも、なた豆の腎臓への効果について書かれたものがいくつもあります。中国の明の時代に書かれ、日本でも江戸時代に和訳された漢方の教科書「本草綱目」の中でなた豆が「腎を益し、元を補う」と紹介されています。医者自身が実感したなた豆の効果
そこで本当に、なた豆が腎臓病によいのかどうか、私自身もなた豆茶を試してみることにしました。なぜなら、私自身が腎臓病を患っているからです。
医者として多忙な生活を続けているうちに糖尿病になり、その合併症で目と腎臓を悪化させ、現在は透析を行っています。
腎臓病は気付かないうちに進行していきます。医師としては反省の極みですが、私は自分自身の病気の兆候を見逃してしまったのです。
腎機能の改善のため、なた豆茶を飲み始めると、徐々に変化が現われてきました。まず足のむくみが改善されました。
むくみは腎臓病の典型的な自覚症状で、透析をしていると、むくみがなかなかとれません。ところが、なた豆茶を飲むようになってから、むくみがだいぶ軽くなってきたのです。
もうひとつ驚いたのは、目に明るさが戻ってきたことです。糖尿病で目を悪くした私は、視野が薄暗い状態だったのですが、最近は明るさが感じられるようになってきました。
また、透析をしていると、ほとんどの人は尿が出なくなります。私もずっと尿が出なかったのですが、最近、少量ではあるものの、尿が出たのです。
また、腎臓が悪くなると血圧も高くなります。私も以前は最高血圧が170以上あり、ノルバスク・コニール薬を服用していましたが、
なた豆茶を飲み始めてからは150以下になり、降圧剤の服用も少なくなりました。これらは腎機能の回復が著しい証拠となります。
※井上隆人先生は、平成30年10月24日にご逝去されました。
生前、井上隆人先生に取材したものです。なた豆を使った患者さんの症例

case01
他院で腎炎の治療を受けていたときは、腎機能の数値であるクレアチニン値がなかなか改善しませんでした。いずれ透析をしなければならないと告げられ、本人はかなりのショックを受けていました。
私が診たところ、確かに数値は悪かったものの、まだ透析を宣告するほどではありませんでした。
そこで、まだ透析の必要はないと話して患者さんの精神的なストレスを取り除き、なた豆茶を飲むように指導しました。
なた豆茶を飲み始めると、しだいに腎機能は改善されてきました。透析の不安から解放されたのか、患者さんの表情も明るくなりました。(20代女性)
case02
他院でクレアチニンの数値が7あり、すぐ透析を始めなければいけないと宣言された患者さんでした。
しかし、当院でなた豆茶をすすめたところ、当初に6.95あったクレアチニン値が、2ヶ月半後には5.16まで改善し、足などのむくみが解消されました。この患者さんも当面、透析の心配はなくなりました。(70代女性)東洋医学から考えるなた豆
科学的なアプローチによるなた豆の効能については、カナバニン(血行促進作用)や、コンカナバリン(抗腫瘍作用)などの有効性成分が多数発見されています。しかし、なた豆が効くのは有効成分の効果だけではありません。
東洋医学の「人の体は薬の宝庫」という考え方を学ぶと、漢方として古くから活用されていたなた豆は、患者さん自身の体の中にある「薬」を高める鍵になるのではないかと私は考えています。
鹿児島市内のなた豆畑を私も見学させていただきましたが、とてもおだやかな「気」を感じました。それもまた、良質のなた豆を作る条件になっているのではないかと思います。
「気」というのは、東洋医学の大切な考えです。東洋医学では体の中にも気が流れているととらえています。
川の流れを想像してください。川がサラサラ流れていれば水はきれいですが、淀んでいると水もにごります。
健康な体は気の流れはもちろん、血液やリンパ液などがスムーズに流れています。逆に病気になると、これらの流れは悪くなります。
私の治療では、これらの流れをよくするマッサージ療法を併用しています。
なた豆を使った患者さんのお喜びの声

なた豆を使った患者さんのお喜びの声
「数値が少しずつでもよくなれば透析が回避できるかもしれません。」K・Sさん(50代・男性)
四十代半ばの健康診断で尿タンパクが出ていることがわかりました。コレステロール値や尿酸値も通常より高く、原因は腎臓にあるということでした。その頃の私は仕事で徹夜が続くなど、無理な生活を続けていました。
今にして思えば、それで腎臓を悪くしたのでしょう。しかし、そのときはなんの症状もなかったので、それほど真剣に考えず、とくに治療はしませんでした。
それから10年ほどたって、血液検査のクレアチニンの数値が2.1と正常値の約2倍にまで上昇し、医師から慢性腎不全と診断されました。このまま病気が進行すると、透析をしなければならなくなるとも言われました。透析の不安から色々調べていると、テレビ番組でなた豆が腎臓に良いという情報を知り、なた豆茶を飲んでみることにしたのです。
なた豆茶を飲み始めて一カ月後の検査では、クレアチニンが2.1から1.7、尿素窒素も33.7から29.2まで下り、さらに尿タンパクや尿潜血の値も改善していました。
今までは腎臓に関する数値は悪化する一方だったので、この変化には驚きました。数値が少しずつでもよくなれば透析が回避できるかもしれません。その為にも、なた豆茶を続けていきたいと思っています。



 MENU
MENU