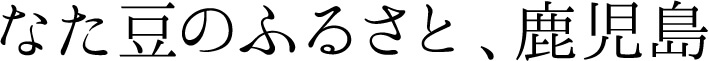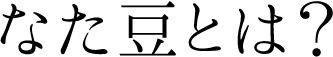マメ科最大級の植物「なた豆」


マメ科最大級の植物「なた豆」
鹿児島県の特産品であるなた豆は、マメ科の1年草で刀豆(トウズ、なた豆)、帯刀(タテハキ)とも呼ばれています。
マメ科1年草としては最大級の植物で、丈は5メートル以上、サヤも40~60センチまで大きく太く成長します。
サヤの中の種子も3~5センチ程の大きさになります。大きなマメとしてなじみのあるソラマメが約3センチですから、それよりもひとまわり大きな豆です。
春先に種をまくと、夏に白またはピンク色の花を咲かせ、秋口に結実します。
亜熱帯アジアが原産とされ、温暖な気候を好み、中国長江流域および南方各省で栽培され、中国では薬膳の食材として用いられてきました。
明の「本草綱目」には、なた豆が漢方医療の生薬として紹介されています。
日本に渡来したのは江戸時代のはじめの頃といわれています。1696年の「農業全書」の中で「刀豆」として記載されています。おそらくサヤの形が、刀や刃物のなたに似ているところから「刀豆」と表記され「なた豆」と呼ばれるようになったのでしょう。
なた豆は生命力が強く、ぐんぐんと勢いよく生長することから、日本各地で縁起の良い豆、商売繁盛のお守りとして親しまれています。
また、地方によっては、花が絶え間なく咲くことから子孫繁栄の縁起物として扱われることもあるようです。
古くから鹿児島で食されてきた「なた豆」

古くから鹿児島で食されてきた「なた豆」
鹿児島でも江戸時代から広く雑穀として栽培されていたようです。
現在、なた豆の農業生産は、思川・本名川・稲荷川という良質の水源にも恵まれる鹿児島市吉田地区を発祥の地として、姶良市、薩摩半島北西の出水市、薩摩半島南西部の南さつま市にまで広がりを見せています。
食用としては若いサヤを福神漬け・ヌカ漬け・味噌漬け・粕漬けなどのお漬物として利用されてきました。また豆(種子)は、薬効成分として健康茶などに利用されています。
ただし、豆類全般にいえることですが、なた豆にもタンパク毒があります。とくにタチなた豆は毒素が多いと言われています。食用には正しい処理が必要となりますので気をつけてください。



 MENU
MENU