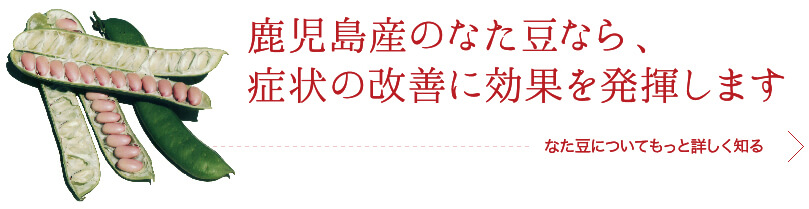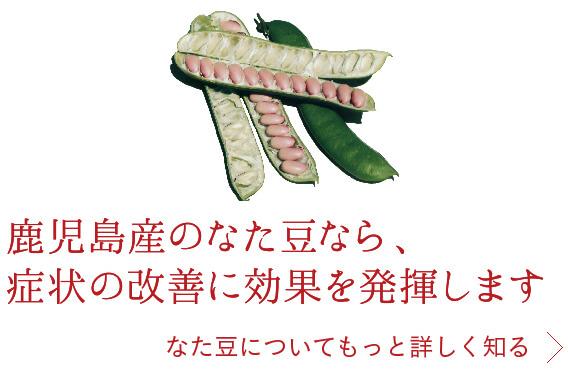蓄膿症

蓄膿症
蓄膿症は、一般的に鼻の病気として知られていますが、医学的な定義では鼻腔だけではなく、体腔(体の空洞)に膿が溜まってしまった状態の事をさしており、「膿が蓄積する症状」ということから蓄膿症と呼ばれています。
慢性副鼻腔炎(蓄膿症)
鼻腔における蓄膿症の正式名称は慢性副鼻腔炎と言います。慢性副鼻腔炎は鼻の奥の方にある副鼻腔と呼ばれる空洞に膿がたまる病気です。
原因は、風邪などによる急性副鼻腔炎や、ひどい虫歯などがあります。
蓄膿症(慢性副鼻腔炎)になると、膿が混じった黄色っぽい鼻汁が流れるようになり、不快な臭いや頭痛などに悩まされる人もいます。
そして、副鼻腔に膿がたまったままの状態が続くと、しだいに鼻の粘膜が厚くなる「粘膜肥厚」が起こり、膿の排泄がより困難になって、症状が悪化していくのです。歯性上顎洞炎(蓄膿症)
また歯が原因で起こる歯性上顎洞炎も蓄膿症の一種です。上顎洞は左右の上顎の骨の中にある鼻腔とつながった空洞で、上の歯の炎症が上顎洞まで達したのが、歯性上顎洞炎です。普通の蓄膿症(慢性副鼻腔炎)よりも症状がしつこく、膿の臭いも強烈なのが特徴です。
さらに進行すると細菌が上顎の骨まで達し、骨が溶けてしまいます。そうすると健康な歯を抜歯しないと治療できないことが多く、入れ歯にしなければならなくなります。
また膿がたまってくると、上顎洞の粘膜が肥厚し、鼻の通りも悪くなります。その結果、呼吸が苦しくなり、鈍重感といった症状が出てきます。
さらに重症になると、眼球を圧迫したり、脳炎を引き起こすこともあります。
歯性上顎洞炎(蓄膿症)について 先生の話


歯性上顎洞炎(蓄膿症)について 先生の話
番町オーラルサージャリ-&スキャニング院長
歯学博士 伊藤道一郎先生
恐ろしい蓄膿症・歯性上顎洞炎
歯性上顎洞炎は、むし歯などにより上の歯が炎症を起こし、その炎症が歯根を貫いて上顎洞にまで達する歯が原因の蓄膿症です。
炎症を起こす原因は口腔内の病原菌で、それが上顎洞に侵入すると、白血球の免疫細胞が集まってきて、これを排除しようとします。
その結果、病原菌と免疫細胞は死滅しますが、その残骸が膿となって上顎洞にたまっていくのです。
歯性上顎洞炎の治療法は、原因となっているむし歯を抜き、それでも完治しない場合は手術します。
状態がひどい場合は全て歯を抜いて総入れ歯になることさえありますので、患者さんのなかには、手術をしたくないという人もいます。
手術を拒否されて治療していた患者さんの中で一人だけ、経過観察を続けているうちに、症状が改善してきた人がいました。
何か特別なことをしているのか尋ねると、その患者さんは毎日なた豆茶を飲んでいたと答えました。様々な口腔疾患への効果が期待されるなた豆
なた豆は歯周病だけでなく、それ以外の口腔疾患への効果が期待できそうだと、効能に興味を持った私は、歯性上顎洞炎の臨床試験を行うことにしました。
その結果、12人の患者さんのうち10人に改善がみられました。改善するまでの期間は、早い人で約二カ月、1番長くかかった人で約1年半、平均で四カ月半後には、患部の回復がみられました。 この臨床研究は『歯性上顎洞炎治療におけるなた豆茶の使用経験』という論文にまとめ、2002年の第47回日本口腔外科学会で発表しました。なた豆を使った患者さんの症例

case01
右上の歯が原因で歯性上顎洞炎を起こしていた患者さんは、上顎洞の粘膜が肥厚しており、鼻詰まりと鈍重感を訴えていました。原因となっている右上の歯を抜歯しましたが、粘膜の肥厚は改善しません。
肥大した粘膜を除去する手術を提案しましたが、患者さんは拒否されました。そこで、なた豆茶をすすめました。
半年後、「鼻の通りがよくなり、頭の重石が取れたようだ」というので、レントゲン撮影してみると、上顎洞粘膜の肥厚が消えているのが確認できました。(40代女性)
case02
左上の歯が原因で歯性上顎洞炎を発症しました。原因となっていた歯を抜き、抗菌剤などを投与して治療を続けました。しかし40日を過ぎても改善がみられないばかりか、抜歯前よりも上顎洞の粘膜が厚くなり、左の上顎洞は完全に埋まってしまいました。その結果、患者さんは眼球の圧迫感や鼻詰まり、鈍重感を訴えるようになりました。
この患者さんも手術は拒否されたので、なた豆茶の飲用を提案することにしました。なた豆茶を飲み始めてから三カ月後、ご本人から「鼻詰まりがまったくなくなりました」といわれたので、レントゲン撮影してみると、左の上顎洞の粘膜の肥厚はすっかり改善されていました。
このように、なた豆は蓄膿症の一種、歯性上顎洞炎に有効であることが証明できました。(26歳男性)
なた豆を使った患者さんのお喜びの声

なた豆を使った患者さんのお喜びの声
「鼻が詰まらなくなり、鼻が気持ちよく通るようになり、鼻水が出ることもなくなりました。」W・Sさん(74歳・男性)
蓄膿症になったのは、中学生のときでした。正しい病名は「鼻茸」といい、蓄膿症の一種で、鼻の中に茸のようなこぶができるので、こう呼ばれています。症状は、鼻水がダラダラ流れたり、逆に鼻が詰まったりします。鼻水が止まらないのもつらいものですが、一番苦しいのは、鼻が詰まることでした。
普段は左右の鼻が交互に詰まるので、まだ我慢できますが、悪化すると両方の鼻が同時に詰まってしまいます。
鼻での呼吸が完全にできなくなるので、寝ているときも口で呼吸しなければなりません。そうすると、口の中が乾燥して、ウイルスに感染しやすくなり、風邪をひきやすくなってしまいました。20年ほど前に、鼻茸を治そうと手術しました。それで一時的には、鼻の状態がよくなりましたが、その後再発してしまい、また鼻が詰まるようになってしまいました。 そこで、蓄膿症によいという評判のあるなた豆茶を飲んでみることにしました。
私は農業をしているのですが、農作業は肉体労働です。汗をたくさんかくので、水分補給は欠かせません。
夏場は2リットル、それ以外の季節でも、毎日1リットルはなた豆茶を飲んでいます。これを続けていると、いつのまにか鼻が詰まらなくなり、鼻が気持ちよく通るようになり、鼻水が出ることもなくなりました。



 MENU
MENU