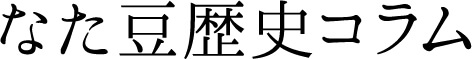漢方生薬としてのなた豆
漢方の古文書に見られるなた豆の記述

漢方の古文書に見られるなた豆の記述
日本では主に食用として利用されてきたなた豆ですが、中国では古くから漢方薬として重用されてきました。明朝の本草学者である李時珍が編纂した「本草網目」は、その内容と網羅された薬草の数において「過去最大の薬学著作」といえる図録であり、中国医学(漢方)を学ぶ者にとってバイブルのひとつに挙げられる名著です。
そのなかになた豆に関する記述が見られ、効用として「腎を益し、元を補う」と書かれています。漢方で「腎」と呼ばれるものは、腎臓を指すのではなく、生命エネルギーの源である「気」を蓄えておく臓器とされます。なた豆はこの「腎」の機能を高めて、病気に負けない免疫抵抗力をもたらす生薬とされています。
加えて、「脾を健やかにし、腎を補い、寒を散らし、腸胃を利す」との効用が記されています。東洋医学でいう脾とは何なのでしょうか。脾は消化吸収の働きを指す総称であり、気と血を生み出す源とされています。脾は胃腸で消化された飲食物を気や血に変えて心肺へ送り、そこから全身に運搬される一連の働きを担っているのです。生命維持のうえで重要な役割を担う脾に対して薬効の高いなた豆は、漢方生薬としても価値の高いものといえるでしょう。
なた豆とは「膿とりの妙薬」


なた豆とは「膿とりの妙薬」
このようになた豆は、東洋医学的な面からも身体によい作用をもたらすものとされています。生薬としてのなた豆の効用を具体的に挙げるとすれば、「血液浄化」「血行促進」「排膿」「消炎」などが挙げられます。なかでも特筆すべきはその排膿作用でしょう。
排膿とは、さまざまな感染症によって作り出される膿を体外へ出す働きで、なた豆はそれを促す効果に優れているといわれています。膿は病原菌と闘って死んだ白血球の死骸ですが、歯槽膿漏や蓄膿症、痔ろうなどの病気でしばしば発生し、病状をいっそう不快なものにしかねません。その膿を素早く体外に出す効用があると古くより認められ、日本の民間療法においても「膿とりの妙薬」として利用されてきました。
食材として、生薬として、なた豆には健康をつかさどる多くのパワーが凝縮されているのです。



 MENU
MENU